| cover | ||
 |
山麓雑記 | |
| contents | お買い求めはコチラ |
蒸気機関車同乗記
蒸気機関車同乗記
いい年齢をして機関車に乗ってみたいなどということはいかにも子供じみてはいるが、誰でも子供の頃から見なれた汽車の、特に機関車そのものに対する憧れは多少とも持っているに違いない。
私の家の隣りの主人三溝さんは永年国鉄に勤務している人であるが、町内のことというと大変な世話好きで随分いろいろお世話になっている。そんなことから時々上り込んで話し合ったり、正月一杯など一緒にやりながらいろいろな話が出ることがある。子供の時から憧れていた機関車に乗りたい希望はその時の話から出たものである。いよいよ蒸気機関車はジーゼルや電気機関車に変りつつあって、この十年位でわれわれの眼の前から消えうせる運命にあるという話やら、三溝さん自身停年を近く迎えることになると何とか機会を急ぐ必要もあり、初めの冗談がだんだん現実化されていった。しかし素人の考えているようにことは簡単にいくものではなく、そのための手続きなど案外むずかしいことが解ってきたのである。
ところが私の関係している松本の月刊雑誌「新信州」が国鉄の現場に働く人達の座談会を計画することになり、私が、その司会を依頼され、予備知識として、松本の機関区を訪ねだりしているうちに、機関車同乗の案も具体的になり、遂に当地方を総轄する監理局に許可申請を出す仕儀になった。幸い三溝さんの上役の口ききもあって許可が下り、松本、長野間往復の機関車にのり込む機関車特別乗車証が下付されたのである。
さて、その日は特に寒い朝で、前から貸与された青色の作業服を着て、打ち合せた駅のプラットフォームに待っていた私の前に止った機関車の窓から三溝さんに声を掛けられ、その方に歩みよっていった。驚いたことにはステップといわず機関車の横腹といわず、吹き出す蒸気が凍ついて、鋼鉄と氷の合成品のような凄さまじい巨大な塊りの機関車に直面させられると、流石にこんなことをお願いした自分の浅はかさがくやまれるような気持になったものである。
よろめく足を踏みしめて、機関車内部に乗り込むと早速、運転者の三溝さんの反対側にある助手常に場を与えられた。そうなると助手君は立ち放しになって気の毒なことになる訳であるが、後で解ったが席はあっても機関助手は全く、それを使って一休みする暇がないほどいそがしく立働かなければならないのである。大体機関車に特別に乗車することを許可されても、多くは後部の石炭車の石炭の上に覆いなどが一時的につけられ、その中から運転席を見ているのが関の山らしいのに三溝さんの好意によって助手席を与えられたのは予想外の幸といわなければならない。
乗り込むと間もなく、列車は長野に向って出発したが、もはやそうなると誰とも話合っていられない位機関車内部はいそがしく、緊張の連続で言葉をかけることさえ遠慮しなければならない厳しさが車内に充満する。またそれと一緒に轟々たる車輪の音、煙突から吹き上る蒸気の音、いろいろな部分から発する機械音、お互に復唱し、確認し合う運転手と助手との言葉の交換、ほとんど休むことのない石炭投入のための蓋の開閉音と汽笛等、全く一時は耳を聾する許りで、初めてのことながら如何に機関車というものは音響に充満しながら行動するものであることが解るのである。
片側は寒風の吹き込むガラス無しの窓と反対側は炉の火に照らされて、身体の半分は寒く、半分は暑い位置に固定されなから、激しい振動と轟音の中で漸次機関車のもつ活動的な雰囲気に引き込まれて行った。これはまた、なんという男性的な生々した感覚と力であることか、凡ての列車の先頭に立って勇壮に身震いしながら牽引して行く。そこには何等の貧弱さ、疲れ等微塵もよせつけない健康にみちた逞しさとエネルギーの持つバイタリティーの美しさがある。芸術家でなくとも、誰でも感じるであろう、ぞくぞくするような感激は詩となり音楽となる充分な要素を蔵している。
燃えつづける炉に間断なく投入される石炭、常に蒸気圧と客車暖房のゲージの確認、重油管の開閉、汽罐への送水管とポンプの操作、常時の機関手と助手との気圧ゲージおよびスピードゲージの確認、進行指示器の確認、駅におけるタブレットの授受等々、まったく機関車運転中は一瞬の遅滞を許さぬ峻厳さで一本の煙草、一言の私語さえさしはさむ余裕など発見できないのである。
どこの勾配は何時何分通過予定、蒸気圧はどの位というように常に往復する場所の細かい認識はまったく時計のような正確さである。これでこそ世界にほこる日本の国鉄の時間表の正確さが守れるのであろう。トンネル内の情景はまた凄壮な絵画を展関する。頭上を逆巻いて流れる煙を照らし出す炉の光と電燈、それは緊張した機関手と助手の顔をも赤々とてらし出す。身体にせまってくる熱気と息づまるようなガスの臭気、戦いに似た感慨が
・・・


 仕事の失敗DB
仕事の失敗DB
 古典語典
古典語典 シニアビジネスは男がつくる
シニアビジネスは男がつくる 「公認会計士・税理士」は資格をとってからが勝負!
「公認会計士・税理士」は資格をとってからが勝負! 税理士、そしてコンサルタントとしての生き方
税理士、そしてコンサルタントとしての生き方 江戸歌舞伎と広告
江戸歌舞伎と広告 久里浜『アルコール病棟』より臨床三〇年の知恵
久里浜『アルコール病棟』より臨床三〇年の知恵 大ノーベル傳
大ノーベル傳 税務調査に強い税理士ご紹介
税務調査に強い税理士ご紹介 TOHO医療に強い税理士紹介センター
TOHO医療に強い税理士紹介センター 東峰書房ショッピングサイト
東峰書房ショッピングサイト 同族会社のための税務調査
同族会社のための税務調査 西洋古典語典
西洋古典語典 東京の季節
東京の季節 ヨーロッパの旅
ヨーロッパの旅 アルコール依存症はクリニックで回復する高田馬場クリニックの実践
アルコール依存症はクリニックで回復する高田馬場クリニックの実践 かしこい医療経営のための税務調査対策Q&A
かしこい医療経営のための税務調査対策Q&A よくわかる医院の開業と経営Q&A
よくわかる医院の開業と経営Q&A クリニックの新規開業を成功させるプロセスとポイント
クリニックの新規開業を成功させるプロセスとポイント IFRSが世界基準になる理由
IFRSが世界基準になる理由 2011年中小企業の税務・会計を展望する~IFRSはどこまで中小企業に関わるか~
2011年中小企業の税務・会計を展望する~IFRSはどこまで中小企業に関わるか~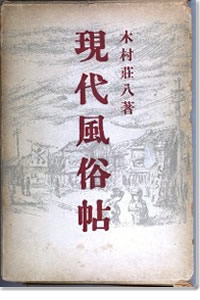 現代風俗帳
現代風俗帳 私のアルコール依存症の記ある医師の告白
私のアルコール依存症の記ある医師の告白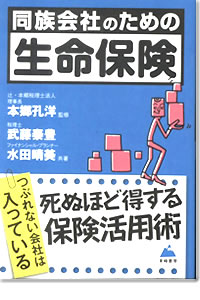 同族会社のための生命保険
同族会社のための生命保険 「税金経営」の時代
「税金経営」の時代 江戸の物売
江戸の物売 江戸の看板
江戸の看板 信州の石仏
信州の石仏 TOHO税務会計メルマガのご案内
TOHO税務会計メルマガのご案内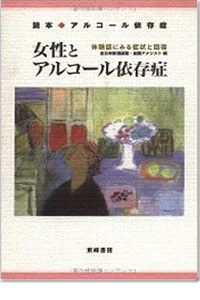 女性とアルコール依存症体験談にみる症状と回復
女性とアルコール依存症体験談にみる症状と回復 版画の歴史
版画の歴史 「断酒生活」のすすめあなたも酒がやめられる《ドキュメンタリー》
「断酒生活」のすすめあなたも酒がやめられる《ドキュメンタリー》 金融マン必携!相続税実践アドバイス
金融マン必携!相続税実践アドバイス 描きかけの油絵
描きかけの油絵 いま、日本にある危機
いま、日本にある危機 「キリストの聖遺物」の謎―どこに消え、誰が秘匿しているのか?
「キリストの聖遺物」の謎―どこに消え、誰が秘匿しているのか? 長生きの国を行く
長生きの国を行く 阿蘭陀まんざい
阿蘭陀まんざい 経営ノート
経営ノート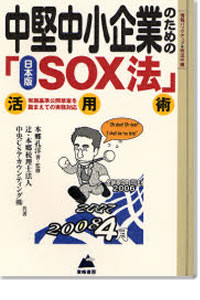 中堅中小企業のための「日本版SOX法」活用術
中堅中小企業のための「日本版SOX法」活用術 グループ法人税務の失敗事例55
グループ法人税務の失敗事例55 バンクーバー朝日
バンクーバー朝日