| cover | ||
 |
山麓雑記 | |
| contents | お買い求めはコチラ |
流れる水
流れる水
京都の河井寛次郎先生をかつてお訪ねしていろいろのお話しを聞いたが、余り沢山の素晴らしい話が後から後からと泉のように流れ出すのに夢中になってしまって、今のようにテープレコーダーというような都合のよいものがなかった昔のこと故、記録する術もなく、話が話の上に重なり合って忘れてしまっているのは今考えると全く惜しくてたまらないのである。
先生自身も感激してきて、自分から涙を流された揚句、特には感極まって、立ち上って踊り出されたことさえあった。民芸の心と現実の仕事との矛盾や斗いの中で苦しんでいた当時の私は京都へよって先生のお話を聞かせて戴いていると、何かしら身内がひきしまってきて、元気が湧き上ってくることが多く、先生の近作の小さな焼物等戴いて御宅を辞してから、五条坂を歩いて下って来るとなんともいえない、すがすがしい気持で一杯になって、やはりお寄りしてよかったという喜びに充たされることが多かった。
先生は御病身でよく風邪を引かれたが、常に大事を取って二階の部屋に引き込まれている時など、折角奥様や先生の甥の武一さん達に迎えられて温かく遇されながらも、何か一沫の物淋しさを感じた。京都の駅から混み合う汽車に乗り込んで田舎の松本に帰って来る時など、窓外の景色も特にわびしく感じられたものである。
先生は信州がお好きで柳、浜田先生やリーチさん達とも、いつも泊られる宿は入山辺の霞山荘であったが、特にあの附近の農家の風情を奸かねてよく散歩された。先生の生まれ故郷り安来り方言にある「立てたった」という暮しり美しさを賞讃されていた。これは先生の書かれたものでも読んだことがあるが、立体的な段階的に建てられた農家の暮しの面白さを語っているものであった。霞山荘から橋倉の部落の辺りまでよく歩かれでいた。
この話も、山辺の村につながるので、他にも河井先生の思い出は多いが特に書いておきたい話の一つである。
詩人キーツの墓にシエレーの書いた墓碑銘というものは有名で私もある本で読んだことがある。その墓碑銘には、「流れる水に其の名を記せし者、此処にねむる」と書いてあるという話である。私達が年若い中学生の頃、よく歌った多分一高の寮歌と思うが、
「流れる水に記しけん、消えて果なき名は追わじ、廻る幾世の末かけて、ただ吾が魂の清かれと……」云々はこの歌の作者がこの墓碑銘から取ったものと思われるが、若い心では何事もわからず、ただ徒らに大声で歌っていたが、それについて河井先生からお話をうかがうとまた改めて感銘の新しいものがあった。
十八世紀以来の西欧の個人の文化、または自我の文化というべき時代に、このような東洋的な悟りともいえる心境の中でこの墓碑銘が書かれたということには一つの驚きがあった。
小さな人間の残す仕事とか、名前というものが、どれだけ果なく悲しいものであるか、世をときめく人達にしたところで、よほどの者でない限り、死後十年、二十年の後にはほとんどが世の中から忘れ去られてしまう。まして信州の片田舎などにおいては果ないというもおろかなことである。当時、著名な人が死後に残す大きな墓を見ると、なんでこのようなことをしなければならないのかという疑問は若い時から時々感じたことである。これはその人の死後の、また一族の虚栄心というべきものであろうかとも考えた。
私は石仏遍歴を長くやったが、そのついでによく墓の形などのよいものなどを見て歩いたことがある。日本のような乾湿、寒暑のはげしい温帯地方ではペルシャやエジプトのような地方と違って石の寿命は甚だ短いといえる。ましてこの辺の大部分の墓石に至っては文字の読めるものはせいぜい元禄位迄であるから三百年から四百年位のことで、それ以前のものとなると珍らしいということになる。ただ墓石があっても誰の墓であるかわからなくなっているし、まして子孫にしたところで最早百年二百年前のことは全く不明となる。また、それで良いのではないか。もし、人間が全部永遠に死後の記しを地上に残さなければならないとすれば、地球上は遠からず墓で掩われてしまうに違いない。
河井先生は山辺の片隅で見た墓の話をされたのである。それは無名の墓であった。その墓は路傍に横たわる自然石で、文字も何にも初めからないものであった。それに季節の花と線香がその日、供えてなかったら、全く一つの自然石として腰を休めるよすがにもなったかも知れないものであった。貧困の故そういう墓ができたのか、初めからの意志でそう作られたのか、多分前者であろうが、これは既にそのようなことを超越して自然の中に融合してしまった墓石であった。
シエレーの墓碑銘さえ、すでにこの墓石の前に出ては色あせて、やはり西洋のカスが残る嫌味さえ感じられると先生はいわれた。
民芸の世界にある究極のものは、そのようなものであった。名前も知られず歴史の塵の中に埋れ去った工人の人工の跡も自然の中に溶け込んで、美しさだけが残されている世界、東洋の幽玄な世界の中の真実、昔の人はこのような世界を求めて、我々のためにいろいろなものを残していってくれたのである。
信州の人情は最も知性的である反面、全くその逆の姿に徹したいろいろな物が民芸の世界から見ると、民間伝承のもののなかに残されていて面白いことである、とはかつて柳宗悦先生のいわれた言葉であった。


 仕事の失敗DB
仕事の失敗DB
 古典語典
古典語典 シニアビジネスは男がつくる
シニアビジネスは男がつくる 「公認会計士・税理士」は資格をとってからが勝負!
「公認会計士・税理士」は資格をとってからが勝負! 税理士、そしてコンサルタントとしての生き方
税理士、そしてコンサルタントとしての生き方 江戸歌舞伎と広告
江戸歌舞伎と広告 久里浜『アルコール病棟』より臨床三〇年の知恵
久里浜『アルコール病棟』より臨床三〇年の知恵 大ノーベル傳
大ノーベル傳 税務調査に強い税理士ご紹介
税務調査に強い税理士ご紹介 TOHO医療に強い税理士紹介センター
TOHO医療に強い税理士紹介センター 東峰書房ショッピングサイト
東峰書房ショッピングサイト 同族会社のための税務調査
同族会社のための税務調査 西洋古典語典
西洋古典語典 東京の季節
東京の季節 ヨーロッパの旅
ヨーロッパの旅 アルコール依存症はクリニックで回復する高田馬場クリニックの実践
アルコール依存症はクリニックで回復する高田馬場クリニックの実践 かしこい医療経営のための税務調査対策Q&A
かしこい医療経営のための税務調査対策Q&A よくわかる医院の開業と経営Q&A
よくわかる医院の開業と経営Q&A クリニックの新規開業を成功させるプロセスとポイント
クリニックの新規開業を成功させるプロセスとポイント IFRSが世界基準になる理由
IFRSが世界基準になる理由 2011年中小企業の税務・会計を展望する~IFRSはどこまで中小企業に関わるか~
2011年中小企業の税務・会計を展望する~IFRSはどこまで中小企業に関わるか~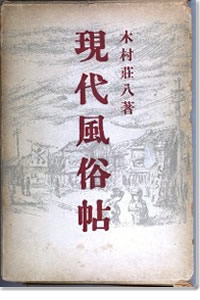 現代風俗帳
現代風俗帳 私のアルコール依存症の記ある医師の告白
私のアルコール依存症の記ある医師の告白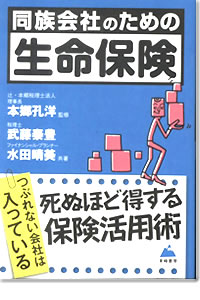 同族会社のための生命保険
同族会社のための生命保険 「税金経営」の時代
「税金経営」の時代 江戸の物売
江戸の物売 江戸の看板
江戸の看板 信州の石仏
信州の石仏 TOHO税務会計メルマガのご案内
TOHO税務会計メルマガのご案内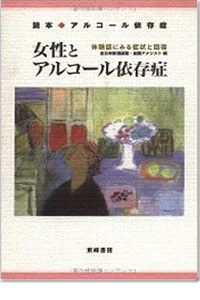 女性とアルコール依存症体験談にみる症状と回復
女性とアルコール依存症体験談にみる症状と回復 版画の歴史
版画の歴史 「断酒生活」のすすめあなたも酒がやめられる《ドキュメンタリー》
「断酒生活」のすすめあなたも酒がやめられる《ドキュメンタリー》 金融マン必携!相続税実践アドバイス
金融マン必携!相続税実践アドバイス 描きかけの油絵
描きかけの油絵 いま、日本にある危機
いま、日本にある危機 「キリストの聖遺物」の謎―どこに消え、誰が秘匿しているのか?
「キリストの聖遺物」の謎―どこに消え、誰が秘匿しているのか? 長生きの国を行く
長生きの国を行く 阿蘭陀まんざい
阿蘭陀まんざい 経営ノート
経営ノート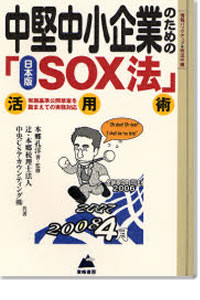 中堅中小企業のための「日本版SOX法」活用術
中堅中小企業のための「日本版SOX法」活用術 グループ法人税務の失敗事例55
グループ法人税務の失敗事例55 バンクーバー朝日
バンクーバー朝日