| cover | ||
 |
山麓雑記 | |
| contents | お買い求めはコチラ |
南極にただ一人
南極にただ一人
七、八年前のことになるかもしれない。偶々読んだリーダース・ダイジェストの特別読物にかつて有名であったバード少将の南極探険の記事があって、少将がただ独りで南極の夜の半歳を観測のため前進基地で暮した手記が出ていた。この記事には私は大きな印象を受け、読み終って興奮のあまりその夜はなかなか寝付かれなかったことを記憶している。
ちょうどその頃よく私の家に遊びに来たNHK勤務のT君にも話したところ、彼も大変感激してその雑誌を買って読んでいたから、彼にとっても終生の記憶として残ったことは間違いない。それほどその記事は世の常の問題からあまりに駆け離れた、人生と仕事、知性と感情の現代的哲学を、現実のできごととして考えさせる驚くべき体験を物語るものであった。
その記事を何かの用に立てるため、小さなテープレコーダーのリールに録音しておいた。一、二度はそれを誰かに借してあげたことはあるが、それが返ってきて戸棚の引出しの中にそのまま保存されて現在に至った。偶々この随筆を折に触れて書き始めてから、独り静かに夜の机に向っていると思い出すともなく、人生のギリギリの問題に対決したバード少将の手記に対する自己の印象を書きたくなってきた。戸棚の中をかき廻わすと、幸いテープを発見することができたので、何年振りかでその時の感激を新たにしたのである。
バード少将 (Richard Erelyn Byrd)は一八八四年に生まれ、一九五七年六十九才で今から十二年前死去しているが、かつて南極の観測が今ほど有名でない初期の頃、スコットやアムンゼンの後から現在の仕事の基を礎いた人であり、南極の開拓者の一人である。
米国の探険隊によって開発された探険基地リトルアメリカは重要であるが、それよりなお二百二十粁奥地の海抜一八○○米のロス氷壁原に辛じて設営されたこの世界最南端たる西南極地域の内陸唯一の観測所におけるバードの半年の夜の行動は南極開発の重要な歴史の何頁かに残されるものであろう。
最初からバード一人でこの観測所で半年を過す積りではなく三人の隊員を配す予定であったが、三月中旬南極へ到着したのが既に遅きに過ぎたり、設営の準備も不足で遂に一人だけしか残れなくなったため、結局隊長バードが責任上進んでその任務につくことになったのである。
バードはその時の心境を「経験のため、全くの孤独と静寂を味ってみたかったし、何か充実した哲学の中に強く根を下してみたかった」といっている。もちろん永年の探険の経験があるから普通の人と違って、難局に処する覚悟や経験が彼にそれを考えさせたことは想像されるが、その考えがいかに甘かったかということが思い知らされることになったのである。何度か死の危機に追いこまれたことがそれを証明することになった。
バード独りだけ残して輸送隊が根拠地に引き返すと半年間の孤独の生活を巾三歩長さ四歩の氷の中に掘られた部屋で寝起することになるのである。
四月は風雪の中に訪れ、寒さはいよいよ厳しくなるのである。零下四十五度になると懐中電気は手に握られたまま、消えてしまうし、四十八度では石油が凍り、ランプの焔は芯の上で乾上り、五〇度となると機械の中の凡ゆる油が凍りついて機械は止まってしまう。どんな僅かな風でもあれば自分の吐く息がカンシャク玉のような音を立て、凍りつくそうである。
ここでバードは孤独との斗いに対して規則正しい日課に精を出すことで対応するのである。が、どんなに努力してみても孤独というものを軽い気持で受け流すなどということはできないほど、時によっては頭もはり裂けるような気持になると告白している。
そんな孤独のうちに四月が過ぎるとますます日は短く、地平線からやっと昇った凄じい火の玉のような太陽も正午には沈んでしまうようになり、それが日一日と短く、暗黒の何ケ月間かが訪れてくるのである。バードは恋人に別れるような気持で沈んだ太陽を見つめて立ち尽すのである。
最近、日本の南極探険隊員で高橋隊員という人が吹雪の日に一寸観測器を見るために戸外に出てその儘行方不明となり、結局凍死してしまったが、これと同じような経験をバードもしてしまうのである。それは運動のために戸外を歩き廻ったが、アンテナのポール以外に数百粁四方には、目標にするものがなく、百米内に三歩毎に竹の棹を立ち込んで目印にした。ある日考えごとをしていて、うっかりその圏外に出てしまったことに気づかなかった。それと気づいた時には氷原上何も目印になるものはなく、懐中電燈で照してみても靴の跡さえ発見できなかった。急に駆け出そうとする衝動に駆られたが踏止まって考えた。ここが常の人と違う、探険隊で訓練された偉いところであったと思うのである。その時彼はどういうことをしたかというと、氷の上に今来た方向の矢印を靴で削って作り、氷の塊で目印にした。そして矢印の先の空に二つの星を目標として、それに向って百歩歩いて見た。しかし何も見えない。それからまた、元の位置に返って、方向を三〇度左に変えて再び百歩歩いた。しかし何も見えなかった。それでも彼はこの時の心の動揺に対し冷静に斗うだけの科学者としての知性を持っていた。そのことが彼を救ったと考えられる。元の標識さえ見失うようなことがあったら絶対凍死は免がれないに違いないのである。彼は基点から百歩の先になお、百歩延長してそこを基点として三十歩づつ、方向をかえてみることにしたが、最初の二十九歩目で十米先に竹の棒を見つけることができた。
五月の初めはもうすでに太陽は地平線下にかくれ、ただ月と向いあって大かがり火のように暗黒な空を燃やす許りであったが、寒さは去り、風もなく、全く無音の世界が訪れてきた。孤独はいよいよその深さを増すのである。ここでも彼は冷静に、客観的に自分をまだふりかえってみる心の余裕を示している。孤独というものは人間の礼儀作法がどの程度まで他人に左右されるかという絶好な実験室であるといっているが、一人切りの生活は外部に感情を表わす必要がなくなるからで、乱暴な言葉等吐く必要はなくなった。ただユーモアの感覚だけが残ったが、それも心の中で笑うだけで、声を立てて笑うにはどうしたらいいかということさえ忘れてしまった、と彼はいっている。また彼は自分の発する大きな声の言葉が聞きなれない空ろなものに響くことを知った。
髭は一週間に一度はすったが髭が凍り付いて顔に凍傷をおこすからであった。毎日周囲に女がいないと男は虚栄心を失うという結論であったが、鏡に写る彼の顔は眼は充血し両方の頬は水ぶくれができ、鼻は赤く百回も凍傷にかかって球根のような格好になってしまったのでは当然の帰着ということができるであろう。
いよいよ厳寒は深まってきた。零下五九度の真夜中、小屋の上げ戸を両肩で押し上げて、戸外に顔を出した時どんなにあえいでも肺に空気が入ってこないことを知ったのである。
ここで彼は壮大な宇宙の神秘であるオーロラ(極光)の巨大な光線の掛幕が途方もない大きなひだを作って南極の上にかかる光景を見るのである。それが消えた時、凡ゆる他人が見ることをこばまれている光景に自分だけが立ち会ったという、大きな感激に立ち尽したが、想像するだけでも凄然たるものを感じさせるのである。
・・・


 仕事の失敗DB
仕事の失敗DB
 古典語典
古典語典 シニアビジネスは男がつくる
シニアビジネスは男がつくる 「公認会計士・税理士」は資格をとってからが勝負!
「公認会計士・税理士」は資格をとってからが勝負! 税理士、そしてコンサルタントとしての生き方
税理士、そしてコンサルタントとしての生き方 江戸歌舞伎と広告
江戸歌舞伎と広告 久里浜『アルコール病棟』より臨床三〇年の知恵
久里浜『アルコール病棟』より臨床三〇年の知恵 大ノーベル傳
大ノーベル傳 税務調査に強い税理士ご紹介
税務調査に強い税理士ご紹介 TOHO医療に強い税理士紹介センター
TOHO医療に強い税理士紹介センター 東峰書房ショッピングサイト
東峰書房ショッピングサイト 同族会社のための税務調査
同族会社のための税務調査 西洋古典語典
西洋古典語典 東京の季節
東京の季節 ヨーロッパの旅
ヨーロッパの旅 アルコール依存症はクリニックで回復する高田馬場クリニックの実践
アルコール依存症はクリニックで回復する高田馬場クリニックの実践 かしこい医療経営のための税務調査対策Q&A
かしこい医療経営のための税務調査対策Q&A よくわかる医院の開業と経営Q&A
よくわかる医院の開業と経営Q&A クリニックの新規開業を成功させるプロセスとポイント
クリニックの新規開業を成功させるプロセスとポイント IFRSが世界基準になる理由
IFRSが世界基準になる理由 2011年中小企業の税務・会計を展望する~IFRSはどこまで中小企業に関わるか~
2011年中小企業の税務・会計を展望する~IFRSはどこまで中小企業に関わるか~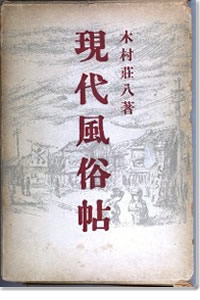 現代風俗帳
現代風俗帳 私のアルコール依存症の記ある医師の告白
私のアルコール依存症の記ある医師の告白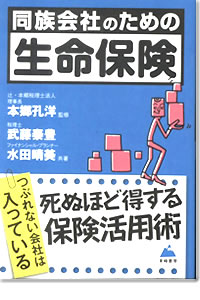 同族会社のための生命保険
同族会社のための生命保険 「税金経営」の時代
「税金経営」の時代 江戸の物売
江戸の物売 江戸の看板
江戸の看板 信州の石仏
信州の石仏 TOHO税務会計メルマガのご案内
TOHO税務会計メルマガのご案内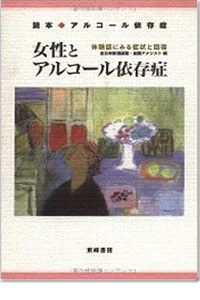 女性とアルコール依存症体験談にみる症状と回復
女性とアルコール依存症体験談にみる症状と回復 版画の歴史
版画の歴史 「断酒生活」のすすめあなたも酒がやめられる《ドキュメンタリー》
「断酒生活」のすすめあなたも酒がやめられる《ドキュメンタリー》 金融マン必携!相続税実践アドバイス
金融マン必携!相続税実践アドバイス 描きかけの油絵
描きかけの油絵 いま、日本にある危機
いま、日本にある危機 「キリストの聖遺物」の謎―どこに消え、誰が秘匿しているのか?
「キリストの聖遺物」の謎―どこに消え、誰が秘匿しているのか? 長生きの国を行く
長生きの国を行く 阿蘭陀まんざい
阿蘭陀まんざい 経営ノート
経営ノート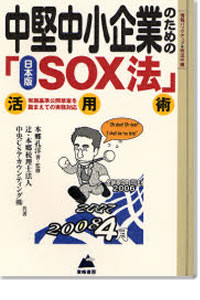 中堅中小企業のための「日本版SOX法」活用術
中堅中小企業のための「日本版SOX法」活用術 グループ法人税務の失敗事例55
グループ法人税務の失敗事例55 バンクーバー朝日
バンクーバー朝日